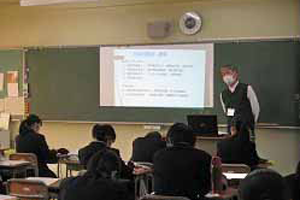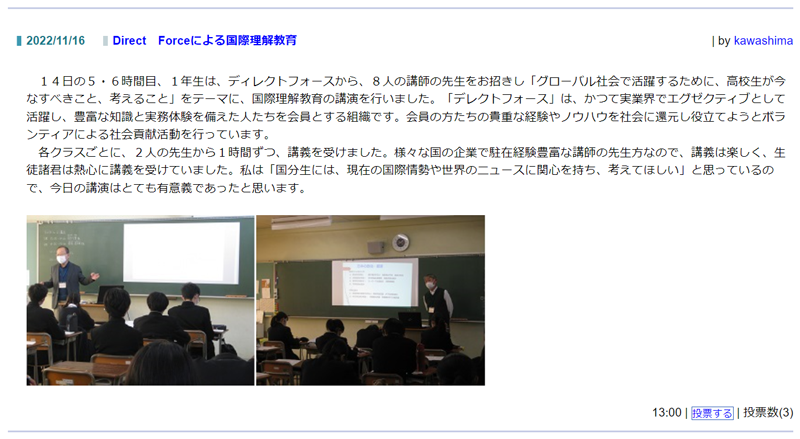掲載日: 2022年12月12日
千葉県立国分高等学校で11年間継続して授業実施
千葉県立国分高等学校では、2012年以来、授業をさせて頂いており、今回11回目の授業を11月14日(月)13:25~16:10に、高校1年生約8クラス約320名を対象に各講師が45分講義を2クラスで行いました。
今回のテーマは、国際理解教育について「グローバル社会で活躍するために高校生が今、なすべきことを考える」と言う主要テーマに基づき、世界、日本、未来、グローバリズム、何をすべきか、どう生きるかなどをキーワードとして各講師がグローバルに関する個別テーマを設定しました。
各講師は、講義45分なかで、講義を中心、質疑応答に重点、一部ディスカッションなど独自に構成を考えながら実体験を交え授業を進めましたが、生徒の皆さんは真面目かつ真剣に授業に参加していました。
授業後に各生徒に記入してもらった振返りシートでは、全体で90%以上が「とても分かりやすかった」、「分かりやすかった」と授業の評価を頂きました。ある講師の授業では100%と高い評価もありました。
また、気付きに繋がったこと、今後に学びたいこと、将来に役にたったことなどについてたくさんの意見・感想を頂きました。
振返りシートの中に各クラス・講師毎に、グローバル社会における自己発信力・コミュニケーション・海外生活・多様性、英語の習得、将来の夢、失敗の時の対応など様々な質問がありましたので各講師からそれぞれの経験を踏まえ回答しました。
また、生徒の振返りシートのデータを先生にフィードバックさせていただき先生からも振返りシートとしてご意見・ご感想を頂きました。生徒は真面目であるが、恥ずかしがり、議論ベタ、失敗を恐れる生徒が多いとのことでしたが、生き方、発信力、コミュニケーション、英語の重要性、疑問を持つ大切さなど講師からの様々なメッセージが伝わり、生徒が生き方を考えるヒントになったとのコメントを頂きました。
修学旅行で台湾に行く予定とのことなので、修学旅行でグローバルな感覚を少しでも身につけて将来に繋げてほしいと思います。
以 上(長谷川 實)
掲載日: 2022年10月27日
仙台市立仙台青陵中等教育学校で授業を実施
仙台市立仙台青陵中等教育学校で昨年に続き2回目の授業を実施しました。
- 日時
- 2022年9月29日(木)10:35~14:50
- 対象
- 5年生(高校2年生)140名
- 形式
- 基調講演+グループディスカッション
今回のプログラムの特徴は以下のとおりです。
- 生徒は2年連続で受講。昨年12月4年生時に実施しており、
今回は2回目のプログラムとなること
- PTA主催行事の一環として企画されたこと。保護者(20名弱)も参観
- 理系、文系別に、午前、午後に分かれて実施(昨年は、全員一堂に会して実施)
今年のプログラムでは、「大きく変化する時代に柔軟に適合していくための心構え、気付きを得ることをねらいとしたい」との要請を踏まえ、事前に担当の先生ならびにPTA役員の方とも意見交換を行い、またZoomを活用し、生徒代表のパネリストも交え、講演内容の確認、当日の進め方など、詳細を打ち合わせ、当日に臨みました。
冒頭の基調講演では、根塚眞太郎会員から「世界を視野に大活躍! 高校生の今、何をすればよいのだろう」のテーマで「コミュニケーション力」、「失敗から学ぶ力」の大切さ、そして「自分で深く考える力」を養うことこそ今取り組むべきと、自らの豊富なグローバル場裡での体験を織り交ぜて講義頂きました。続いて生徒代表4名ならびに授業支援の会メンバー4名(根塚眞太郎会員、見目久美子会員、永合由美子会員、盤若浩孝会員)による、パネルディスカッションならびにフロア全員との意見交換・質疑応答を行いました。
生徒の皆さんからは「日本人も普段から自分の意見をもっとはっきりしてはどうか」、「SNSなど、相手の意見に自分の意見が上書きされてしまう。どうすればよいか」、「自分はコミュニケーションが苦手。良い聞き手になるにはどうすればよいか」、「グローバル化とは日本人を捨てることか、欧米人になればよいのか」、「大変化についていく必要が本当にあるのか。昔の文化をもっと尊重してもよいのでは」などなど、核心を突いた意見・質問が次々出て、コメント、回答するにも正に真剣勝負の場となりました。講師にとっても、今回は「教えることは、学ぶこと」を改めて実感したプログラムとなりました。
また今回の保護者主催によるプログラムは、授業支援の会にとって初めてでしたが、先生・保護者が一体となって企画され、生徒の成長を温かく見守り促す姿勢と取り組みに、講師一同感銘を受けました。
主催者PTA役員の方からのご感想
-
「生徒1人ひとりの屈託ない意見を真摯に受けとめ、講師の皆様が丁寧に応対する姿を拝見して、非常に感動いたしました。おそらく生徒の皆さんも同じように感じてくれたのではないかと思います。不思議と言葉の一つひとつが胸にしっかり入ってくるのを感じました。今回のような生徒とのインタラクティブな授業を参観するのは初めての経験で非常に興味深く、青陵生のみんながあのように自由に発言できる姿をみてとても羨ましく思いました。帰ってきた息子とも話しましたが、とても楽しかった!とのことでした。」
先生方からのご感想
-
「昨年から引き続き2回目ということもあり、よりリラックスした中で、思ったことを純粋に“自由に”述べているように思いました。純粋さゆえに難しい質問にしっかり応えている皆様のご経験と叡智を尊敬いたします。保護者の皆様も、生徒達の成長に感心していたようです。とても満足されておりました」
-
「昨年度からの成長には目を見はるものがあります。自分で考え、積極的に行動する生徒がとても増えました。昨年度の講演会や今年の講演会で、生徒は多くの刺激をもらって大きく成長しているのを私自身は感じております。またパネルディスカッションでは、生徒の質問や意見に驚き、どのような質問に対してもすぐに的確な返答をされる皆様に驚き、感動しております。生徒たちには、この講演会で考えたことや感じたことを大切にし、自分の未来を切り拓き、様々なところで活躍してほしいと思っています」
以 上(盤若 浩孝)
掲載日: 2022年10月27日
田園調布学園中等部・高等部との取り組み
9月22日に同校、副教頭・教務部長の入先生、ICT教育推進部長の村山先生にご講演を頂き、会員一同大いに学ばせて頂きました。これを機に、2014年来大変お世話になっている同校との取り組みを経緯と共に紹介します。
= 次に繋いでいきたい先輩達のレガシー =
授業支援の会は昨年10周年を迎え、記念誌を発行しました。
調布学園(田園調布学園中等部・高等部)の西村学園長からも寄稿を頂き、2013年に黒崎さんのご紹介でコンタクトが始まり、発展し今日に至っている歴史を参照し、支援の会の貢献に謝意を頂いています。
2014年にはトライアルの6講座、2015年からは同校のユニークなプログラムである、土曜プログラムでの授業受託が本格的に始まりました。
土曜プログラムは約170有る講座から生徒が自分で選択し、8回(1回で2限)/年のカリキュラムを自ら作り学ぶと言うもので、マイプログラムとコアプログラムがあります。マイプログラムは「世界を生きる」等5つのテーマから、生徒が関心のある物を自由に、学年の垣根を越えて選択する仕組みで、リベラルアーツ的性格のプログラムです。コアプログラムは学年毎にテーマを設定し身につけたい力を明確にしたプログラムで、探究的要素が含まれます。授業支援の会は両プログラムでお手伝いをしてきました。本年度から移行される、高校の改訂学習指導要領に謳われている探究学習の準備段階として、2019年よりコアプログラムにて、同校の先生を中心とした探究プログラムが始まりました。その際に、藤村さんが高校のコアプログラムで実施されていた、イノベーションコンテスト(AI活用、コンビニの新規事業提案シミュレーション)が評価され、探究プログラムの中でマーケティングとして2講座受託しました。
2022年度からは、探究的学習は学校の正式カリキュラム(中1~高2)としてスタートし土曜プログラムは、従来のマイプログラム型講座1本になりました。授業支援の会は、「視野を世界に」の大テーマで8講座、自由テーマで5講座、マーケティング講座の後継になる4回連続講座を2講座、計15講座を受託しました。会員の皆さんに積極的に参画頂き、心の籠もった授業を展開して頂いており、学園から高い評価を頂いています。
同校は2018年からクロームブックの配布環境を整え始め、20年には中1から高3まで1人1台体制が完成、ICTを積極的に活用し、コロナ禍での勉強の遅れは最小限で済んだ由です。
一方、探究的学習の導入に当たっては、早くから対応され、中学1年から高校2年まで、計画的なカリキュラムを組み、成果を上げられています。現在中等教育の焦点となっている2点で大変進んでいる同校から学ばせて頂こうと、副教頭・教務部長の入先生と、ICT教育推進部長の村山先生に9月22日の例会に合せ講演を頂き、会員の皆さんからは多くを学び得るところ大いであったと反響を頂いています。
土曜プログラムについては「探究に繋がる基礎になったと思う」、「もっと受験に直接役に立つ事をやるべきではないか」と言う考えも有ったが、続けてきて良かったと感じている。「本プログラムに対する授業支援の会の貢献に感謝している」と言う趣旨のコメントを西村学園長にご挨拶した際に頂いています。
先輩達の築かれた素晴しい関係と実績を更に発展させ、次に繋いでいければ、と願う次第です。
以 上(授業支援の会 水口 泰介)
掲載日: 2022年9月20日
ある高校生Aさんへの回答
ある高校で「授業支援の会」が高校生向けに講義したとき、生徒のAさんからの質問に遠藤恭一会員(454)がメールで答えた内容を報告します。
「授業支援の会」で高校生向けに講義をすると生徒の皆さんから質問が来る。そうした質問にメールで答えた内容をご披露します。
Aさん、メールありがとうございます。真剣に将来に向き合う気持ちには敬意を表します。
ご質問ですが下記回答致します。
1)リーダーに必要な人格とは:
あなたの目標はお金を稼ぐこととありますが、一番に考えなければならないのは稼いだお金で何をするかです。お金を稼ぐことは手段であって決して目標ではありません。
お金を稼ぐという目標を立てるだけでは失敗する可能性が高いです。なぜならお金は無色透明なものであり、使う人の意思によって素晴らしいものにも成り、全く邪悪なものにも変化します。単に自己満足の為にお金を使用する様なことでは、誰もあなたに付いてこないでしょう。世の中の指導者的な立場を目指している考えているのであれば、単に稼ぐと言う非常に小さな狭い範囲の考えではその達成は難しいでしょう。例え起業して会社がある程度大きくなったとしても、明確な方針、高い倫理観や規範を持たない単に金を儲けるだけの会社が成長することはないでしょう。あなた自身も金儲けだけを考えている人に一緒に仕事をしたいと思いますか?
本当に世の中に貢献できる高い理想や理念が無ければリーダーになることも出来ませんし、例えお金を稼ぐことに成功しても空しい感覚しか残らないでしょう。
日々の規律ある生活、しっかり深く考えた複眼思考での、ものの捉え方も重要です。そうした中であなたが本当にどの様に、また何を持って世の中に貢献するかという気持ちと心構えが必要です。自分の好きなこと、集中しても飽きないこと、また限られた人生の時間の中で本当に自分のやりたいことを見付けることも結構難しいものです。講義で申し上げた様にあなたは、いろいろな体験・経験をしてその中で何を持って貢献するかまた何に興味があるのかを探ることから始めてください。
私は「リーダーのとしての人」の魅力とは、その人がどんな人生観を持ち、その発言や行動に教養と経験・体験が醸し出ていることだと思います。
あなたは未だ経験も体験も少なく社会に出るまでは多少の時間があるので是非こうした体験・経験を積んで下さい。
2)人脈を作るコツ、気を付けるべきこと:
先程も申し上げましたが、豊かな教養や歴史への深い洞察と理解、時代を読む洞察力。そうしたものが自分に備わっていないと人脈を作ることは出来ません。まず魅力ある人物に自らがならないと人脈を広げることは難しいでしょう。あなたが近づきたいと思う様な人物にあなたがなれれば人は寧ろ向こうから集まって来るでしょう。人生とは何かと考えること、自立して思考し戦う為の武器を持つことなどに真剣に取り組んで下さい。あなたの今の年齢からすると、講義でも申し上げた一人旅や、孤独な一人だけの時間をもって世の中を見つめること、これからの人生をどう生きるかのヒントを得るためいろいろな人に会う事も重要だと思います。あなたの祖父母、親類の叔父叔母、学校の先生、クラブの先輩、兎に角出来るだけ多くの人に『どう生きて来たか』の話を聞くことから始めると良いでしょう。あなたが今出来ることを全てやる意気込みが重要だと考えます。
3)自分が苦手なタイプの人とうまくやっていくには:
実はあなたが苦手な人とは、多分あなたが持っていないもの、考えていない範疇からの発言等がある人ではないでしょうか。勿論
馬が合わないと言った人もいるでしょうが、その人の良い面を見る努力をすることでしか、上手くやっていくコツはないでしょう。若いあなたであれば、苦手などは考えず積極的に付き合っていくことをお勧めします。社会に出れば理不尽な発言をする人や、行動する人が一杯います。
そうした中で自信をもって生きるのはいろんな人が世の中にはいるとの理解でしょう。
4)経営に携わって初めてわかったことは?
先ず、企業組織では人は皆互いに良く見ているということ。人の評価は殆ど変らないこと。「彼は、彼女はこんな人ではないか」といった評価で大多数の人が見る眼は必ず一致すること。経営幹部は常に人を探していること。即ち、この新しい仕事は「彼に、彼女にやってもらおう」と優秀な人材を探していることが上に立って初めて判りました。自分も常に人を探していたことに気付いたわけです。
もう一点、人生には近道やこうしたら簡単に出来る様なHOW-TOの様なものは殆ど意味を持ちません。近道はないと言っていいでしょうし、常に新しいことに挑戦し続ける中で開けて来るものではないかと感じました。RISKから逃げてしまうRISKの方が大きいでしょう。常に新たな挑戦を心掛けて下さい。
最後に:
あなたは突然この世に生まれ落ちた訳ではありません。連綿と流れる歴史の中で、生を受け、この日本という国の中で生活をしている訳です。なぜこの様な生活があり、種々の問題が起きているのかは、実は長い歴史や我々の祖先たちが苦労して築きあげて来た裏付けがあるのです。なぜ先の太平洋戦争で敗戦となったのか、また我々の生きている社会が未だ矛盾に満ちており、決して理想の姿でもありません。物事を単純化して考えるのは非常に危険です。ある物事を自分で判断するには賛成の本を3冊、反対の本を3冊程度読んでどちらが正しいのか、あるいは正しい判断の様に見えるのかは自分で考えることです。是非すべてに冷静に対応して下さい。
以 上(遠藤 恭一)
掲載日: 2022年9月1日
早稲田実業学校中等部で10度目の講演
早稲田実業学校中等部では、私たちは2019年から「特別の教科 道徳」の一環で、パネルディスカッションや講演を行っています。これまでの実施のテーマは下記の通りです。
2019年
- 藤村峯一
- 人生100歳を生き抜く~どう生きるか、仕事とは何か、何が必要か
- 加藤信子
- 身近な材料 “ゴム” との研究生活 ~そもそもの始まりから、研究内容の変遷と広がり
- 遠藤恭一、藤村峯一、川﨑有治 パネルディスカッション
多様性 (Diversity) を考える 「君は何に挑戦したいか」と問われたら
~これから皆さんに求められること
- 高橋民夫(元文化放送)
過去の災害に学ぶ~正しく畏れよう~
2020年
- 水口泰介
- グローバル化が進む世界で今何が求められているか「SDGs 食べるから見える世界
~世界の飢餓と国連WFPの活動」
- 野口明彦
- 医療現場から見た医学。医療倫理の変遷と課題
- 赤堀智之
- 野生動物との共生
2021年
- 藤村峯一
- 公共の場での行動やマナー
- 牧野義司(元毎日新聞経済記者、元ロイタージャパン編集長)
メディアと報道と守るべき人権、そしてSNS書き込みによる人権侵害
今回が節目となる10度目の講演で、見目久美子会員が「災害大国 日本 ~リスクにどう備えるか」をテーマに講演を行いました。
【報告】早稲田実業学校中等部
- 日時
- 2022年7月12日(火) 8:40~9:30
- 対象
- 中等部1学年~3学年(約600名)
- 形式
- 通常は大講堂に集合するが、今回は修繕中のため、各教室の生徒に放送室からオンラインで配信。意見・質問はチャットで受付ける形で実施。
- テーマ
- 防災教育「災害大国 日本~リスクにどう備えるか」
- 講義内容
- 災害への備えや非常時対応に加えて、重要な機能を早期復旧し生き残る『レジリエンス』の大切さについて話した。
- また、非常時に求められるリーダーの振る舞い、パンデミック(現在蔓延中の新型コロナなど感染爆発)への対応についても話した。
-
2件のケーススタディ(家族のレジリエンス、避難所のリーダーに求められること)について生徒間で話し合い、結果をチャット(Zoom)で提出。いくつかをピックアップして講師がコメントし全体共有した。
- 講義を終えての感想
- オンライン配信のため、講義中の生徒さんの反応が見えなかったのは残念でした。
-
ケーススタディ検討結果として、説得力のある意見、独創的な意見など、短い検討時間にもかかわらず様々な意見がチャットで寄せられました。多くの生徒さんが今回授業の本質を理解し自分なりに考えを発展させている事に、安心するとともに生徒さんの力をたのもしく感じました。
-
生徒さんが将来、レジリエンスの重要性を理解したリーダーとして、各分野で活躍されることを願っています。
-
ご担当の小林先生、増山先生には、事前打合せでの内容レビューから当日の授業運営まで、大変お世話になり感謝申し上げます。外部講師による多様な授業を、将来生徒さんが進路選択や生き方について考える時に活かして欲しいという強いお気持ちを感じました。
見目先生の授業を拝聴して
「危機から脱出する時、一番大切なものは何だろうか。」もちろん身の安全を確保することが何よりも大切だが、その後のストレスに対処することも重要な問題だ。大規模災害後、いわゆる災害関連死として亡くなる人は多い。こうした悲劇を繰り返さないためにも何らかの精神的支柱を持つことが、その後の世界を生き抜く大きな要因になる。見目先生の授業は、そうしたことを生徒に訴えた授業であるように感じた。
授業のキーワードである「レジリエンス」という言葉は、あまり耳慣れない言葉ではあるが、昨今の社会において必要とされる力の一つであり、教育の面でも注目されている。授業では、見目先生の豊富な災害支援の経験に基づき、「この時どうすべきか」といったことを生徒に考えさせ、活発な意見交換が繰り返された。Zoomを利用した限られた条件下での授業ではあったが、先生の思いは、しっかりと生徒に伝わったと思う。
災害に限らず、日常の学校現場においても「レジリエンス」の持つ意義は大きい。この授業を通じて改めて回復力の問題に注目してみたいと思った。
(早稲田実業学校 教務部主任 増山 秀樹 先生)
以 上(見目 久美子、藤村 峯一、川﨑 有治)
掲載日: 2022年6月22日
新たな試み:出前講義@都立産業技術高専
授業支援の会 池上 眞平(859)
出前講義@高専の開拓への挑戦の一環として、5月17日に出前講義@都立高専を担当した。
高専サイドの要請を踏まえて、 AIスマート工学コースの2年生の学生38名を対象にタイトル‟研究開発の醍醐味‟の講義(90分)を実施した。
この講義を‟彼らの心に響く/沁みる一時‟とするには、「私の実体験を取上げるのがベスト」は、明白である。
また「‟銀塩写真フィルムを全く知らない学生達が、私の体験を別世界の遠い過去の出来事と思うリスク‟への対策が必要である」も論を俟たない。(注:私の主たる専門分野は、物理化学、固体物理学および写真科学)
さらに、「‟講話後のグループ討論への全員の積極的な参加の実現‟は難しい」を以前から感じていた。
下記点が、出前授業への新たな試みに繋がった。
- 様々なバックグラウンドの人達との意見交換の結果を踏まえた、「‟生徒/学生にとって必要な学び/気付き‟に関する仮説構築」(注:私の独り善がり防止のために、以前より様々な機会を捉えて実施して来た。)
- 「‟学生が私を身近な存在である‟と少しでも感じる」のを狙って、子供〜学生の時代の小生の経験&小生の若手社員時代の経験を導入部に挿入
-
‟他人の意見に惑わされずに自分自身の意見を簡潔に纏めるトレーニング‟を狙った‟感想/意見/質問の文章化の個人ワークのセッション‟の導入
- 個人ワークの充実を最優先するためにグループ討論を省略し、学生達の意見/感想/質問への返信を後日に実施
- 「このトレーニングは、英語による意見交換/討論のスキル向上にも有効」が、私の経験
下記点より「学生達の高いポテンシャル」および「講義@高専開拓への好感触」が、私の印象に残った。
-
学生達からの「68個の多様かつ鋭い質問」と「多様かつ本音を感じさせる感想/意見」(注:個人ワークのセッションでは‟落ちこぼれゼロ‟の方針を取った。先に書き終えて遊ぶ学生が居なかったお蔭で、‟慣れない課題のために筆が進まなかった学生達‟が書き終わるまで静かに待てた。)
-
講義後の担当の先生達のポジティブな感想と彼らとの共鳴を感じる活発な意見交換
-
出前講義@高専に関する国立高専機構の理事長との意見交換の際に‟新たな試み‟も提起したが、‟高専開拓‟に対する我々の努力に対する感謝&励ましの言葉も貰った。
私は、「‟授業支援の会の皆様の多様な経験に裏付けられた講義が、高専の学生達の貴重な成長の糧となる‟のを期待できる」と感じた。
‟この新たな試み‟の実施のために周到な準備をして下さった大野准教授およびこの講義の実施のための事前準備にご協力下さった先生方に感謝するとともに、出前講義@都立産業技術高専の更なる発展を期待している。
以上
掲載日: 2022年6月16日
学生どうしがお互いにアドバイスし合い、学生自からが気づきを得る
東京都立産業技術高等専門学校 情報システム工学コース
講義の背景と概要
東京都立産業技術高等専門学校は「社会と協働し学生の礎を築く」を大きな目標とした教育活動をされています。具体的な教育到達目標のひとつに「コミュニケーション」があげられており、今回の講義はそれに焦点をあてることにしました。
講義概要は次のとおりです:
- 講義テーマ:「自分の未来を創ろう!スーパーエンジニアの先」
- 参加学生:東京都立産業技術高等専門学校 情報システム工学コース2年生 38名
- 実施日:2022年4月25日 90分 x 2
講義の進め方
以下の進め方としました。この中ではステップ3にもっとも時間を割きました。:
- 講師からの説明#1
- グループディスカッション#1
- 全グループからの発表と、その発表に対する全学生どうしおよび講師からのツッコミ#1
- 上記1、2、3を、異なるテーマを取り上げもう一度繰り返す
1. 講師からの説明#1:
まず、講師自身の、グローバルな場における仕事で体験した、成功や失敗あるいは学んだことで、学生のみなさんの将来に役に立つと思われる事例を具体的にお話ししました。その中で、特に、「コミュニケーション力(言語、自分の意見+相手の意見)」を具体的に学生の皆さんに考えてもらうよう講義を組み立てました。グローバルな場でのコミュニケーション力というと、すぐに「英語力」と言われますが、それだけではないことをここでは強調しました。
2. グループディスカッション#1:
ここでは、「コミュニケーション力をあげるにはどうすればよいか」という課題に対して、その答えを学生自ら考えてもらうために、彼らに大谷翔平選手のマンダラチャートを使ってもらい、学生のみなさん自身で解決策を議論してもらいました。
グループディスカッション中に、講師による各グループへの「ツッコミ」
3. 全グループからの発表と、その発表に対する全学生どうしおよび講師からのツッコミ#1:
学生の皆さんの講義への参加意欲を上げるために、ここでは、ややユニークな方法をとりました。例えば次のとおりです。
- グループ1が発表
- 予め講師が決めたツッコミ・グループ(例えばグループ2)の4人全員(4人全員です。)は、グループ1の発表を聞きながら、その発表に対して良い意味での「ツッコミ」をメモし準備する。
- グループ1の発表が一段落したら、グループ2は、ひとりずつ、かつ全員、考えたツッコミをグループ1に対して発言。
- 発表しているグループ1は、グループ2の4人それぞれからの想定内もしくは想定外のツッコミに対し、発表しているその場で頭をしぼりながら回答。
- さらに、講師がより深堀した「ツッコミ」を行い、発表グループに、より深く考えてもらう。
- 上記をすべてのグループが発表グループ、ツッコミ・グループとなるよう繰り返す。
上記の①から⑤の間では、グループ1もグループ2も真剣勝負になります。また、その時点では未だ発表やツッコミの順番がきていない他のグループも、必ず自分の発表あるいはツッコミの番が回ってくることがわかっていますから、この発表グループとツッコミ・グループのやりとりを真剣に聞かざるを得ません。
このやり方に学生の皆さんが馴れてもらった後、より難しいテーマである「講師が外資系IT会社・日本法人の社長の時に実際に経験した、非常に難しい問題を取り上げ、学生のみなさんならどうするか」について、同じやり方でグループディスカッション・発表・ツッコミを行ってもらいました。
伝えたかったキーメッセージ
二つのグループディスカッションのテーマは、表面的には異なるものでしたが、その底流にあるのは、以下の共通したキーメッセージでした。
- 「真のコミュニケーションを図るためには、英語や日本語といった言語だけでなく、相手の文化や価値観まで、お互いに理解し合う必要がある。」
- 「世の中の課題の多くは、答えが多様であるか、答えのないものすらある。この課題を解くには、自分の頭で、深く、深く、考え、行動し、その結果に自分で責任をとる必要がある。」
- 「上記のことは学生の皆さんが、チーフエンジニア・スーパーエンジニアになっても、どのような職種に就こうとも通用するし、今から準備したい、今から準備できるスキルである。」
学生の皆さんからの感想:
-
現実のケースを用いたディスカッションは楽しかったので、もう少しやりたかった。付箋を使って考えを広げていくのは楽しかった。英語シャワーなら、自分にもできそうなので、ラジオAFNの聞き流しをやってみようと思う。
-
高専は基本的にエンジニアを育成する学校であるので、自分はエンジニアになるという狭い視野でしか将来について考えられていなかった。しかし、今回の講師のようにエンジニアから営業、そして社長というキャリアもあるのだなと知ることができ、さまざまな可能性を考えながら自分のやりたいことをしようと感じた。
-
失敗するよりも、失敗を恐れて何もしない言わないことの方がいけないと思うことができました。ときには失敗することも大切で、それを経験して次にどう活かすかが大切だと考えられるようになれました。
-
コミュニケーションを鍛えることが将来の就職活動や、生きるために大切だと感じた。これからは、言葉のキャッチボールや自分の意見をしっかり持つということを意識して生活しようと思った。
-
日本国内だけで生きていく(成り立っていく)のは不可能のため、海外とコミュニケーションを取れるように、また、海外の技術も活用できるようにしていかなくてはならないと感じた。
ご担当の先生からの感想:
-
本講義やグループディスカッションでは、講師の学生への熱いメッセージに学生も感化され、活発なグループディスカッションが展開されていた。
-
日本と他国のコミュニケーション力の違いを学生に体感させることができた。
-
国際的に活躍した方が講師ではないと実施不可能な講義であった。
-
若い学生に国際的な肌感覚を考えさせるよい機会となった。
-
国際ビジネスの中で活躍された講師を通じ、国際的なビジネス感覚とはどのようなものか教育機関だけでは得られないものを学生は得られたのではないか。
講師の感想
この講義を通じて非常に印象的だったのは以下のとおりです。
-
全学生が、ひとり残らず、自分の意見を発言してくれた。
-
グループディスカッションやツッコミは非常に活発であった。
-
コミュニケーション力を強化するために学生が自ら考え、自ら気づきを得たのではないか。
このような講義ができたのは、以下の要因があったからだと考えます。
-
学生自身に、高いモチベーションや授業への参加意欲があった。
-
先生方との事前の打ち合わせにより、先生方の狙い・目的等が理解できていた。
-
講義時間が合計90分 x 2という異例の長さを確保いただいた。
全般を通じて、全学生が積極的に参加した、とても活動的な講義になり、学生の皆さん自身が、グローバルな場でのコミュニケーション力の重要さを自ら気づいていただく一助になったのではないかと考えます。
以上
(授業支援の会 根塚 眞太郎)
掲載日: 2022年4月8日
授業支援の会 10周年記念合宿を実施
授業支援の会は昨年10周年を迎え、「変化に対応する/変化を仕掛ける/変化に挑戦する」を統一テーマに3月16日~17日にセミナーハウス クロス・ウエーブ府中で記念合宿を行いました。
研修スケジュール
3月16日
- 記念講演:
「高等学校側から見たディレクトフォースの意義と期待について」
仙台市立仙台青陵中等教育学校 教頭 若林春日先生
- 会員の講義例紹介:
藤村、太田、牧草 3氏の講義紹介と意見交換
3月17日
- 各分科会の進捗状況の発表:
- 「授業内容の充実」
- 「授業スキルの向上」
- 「新たな会員獲得と新規開拓」
- 5年後に向けてのアンケート結果報告と討議
【記念講演】
『高等学校から見たディレクトフォースの意義と期待について』
仙台市立青陵中等教育学校 教頭 若林春日先生
若林先生には、宮城県仙台第二高等学校ご在職中に、同校の東京研修をお手伝いする機会を頂いた(グループワークの講師として10名以上を派遣)。現職にご異動後も、仙台二高の授業支援を続けることができ、昨年で6年目を迎えた。また青陵中等教育学校でも、昨秋に高校1年生を対象に基調講演&パネルディスカッションを行わせて頂いた。
教育現場の話を学びたいという私共のたってのお願いに、年度末のお忙しい中にも拘わらずご快諾頂き、今回の講演の実施に至った。
講演は二部構成で、第一部では「授業の展開方法」についての講義、第二部ではDF授業支援の会の活動に関わるお話をいただいた。
第一部では、ご自身の専門である高校の「生物」の模擬授業をしたうえで、教え方についての解説があった。私たちにとっては、生徒として聞く体験と、教授法を学ぶという二つの機会を得ることができた。
第二部では、まず、様々な学校での経験を踏まえながら教育の現状を教えていただいた。教師にとって「異動は、転職に等しい」という言葉に、現場の多様さ、難しさを痛感した。
次に、DFの活動の意義について、さらに、学校の教師や地域の制約や限界を超えて、日本の未来を担う若者に対して期待するメッセージや活動を語っていただいた。
【会員の講義例紹介】
若林先生の講演に多くを学び、今後の活動への指針を頂いた後に、日頃なかなか聞く機会のない他のメンバーの講義例の紹介を通して自分の講義を見つめ直した。
【各分科会の進捗状況報告】
各分科会からの更なる活動のレベルアップに向けての中間報告を受けた。
- 「授業内容の充実」
- 「授業スキルの向上」
- 「新たな会員獲得と新規開拓」
【5年後に向けてのアンケート結果報告と討議】
事前に実施した「5年後に向けてのアンケ―ト」結果に基づき将来を語り合った。
コロナ感染のまん延防止等重点措置の終了が翌週に見込まれたものの、まだまだ収束を見ない中、感染対策を充分に行った上での合宿開催でしたが、久々の皆さんとのリアルでの真剣な討議と笑顔との再開で充実した時間であった。
以上
(授業支援の会 内山正人、藤吉文子、川﨑有治)
掲載日: 2022年3月3日
SDGsも意識した、社会にでるための準備とは?:
オンライン環境下の双方向授業へのチャレンジ
沼津市立沼津高等学校
沼津市立沼津高等学校より下記のようなご依頼がありました。
- 日時 : 2022年2月1日(火)、13:20~16:10
- 方式 : 対面授業 講義(50分)+ W.S.討議(50分)+ 発表、意見交換(50分)
- 生徒 : 高校2年生 200人を12グループ分割
- 統一テーマ :「社会に出る為の準備、必要なことは? SDGsも意識して」
- 学校のご要望 :「生徒たちができるだけ討議、意見交換、質疑応答をしてほしい。講師一人に3コマの時間を取ったのはその願いがある。」
講師選定と準備まで
このご要望にお応えすべく、授業支援の会では様々な経歴を持つ講師陣12名の応募を受け、学校側と数度にわたりご相談の上次のような進め方にしました。①講師それぞれが実施したい授業概要を学校側にご送付。②その授業概要を生徒が見て、自分の参加したい授業を選択。(先生による人数調整一部あり)
学校側の強いご要望である討議・意見交換・質疑応答に対して、どの講師も一方通行の授業でなく、グループディスカッションや発表を含む授業方法を準備。また、生徒のみなさんが授業に興味を持ってもらうために、授業に動画やゲームを取り入れようと準備する講師、グループディスカッション中に各グループを移動してアドバイスしようと準備する講師もいたほどです。
急遽オンライン授業へ
2022年1月になって、急遽、コロナ禍のために当初想定した対面授業からオンライン授業に変更せざるを得なくなりました。とはいえ、先生方からは「オンラインでも、生徒たちの討議、意見交換、質疑応答のために、可能な限り工夫してほしい。」というご要望があり、本番の2月1日までの時間的余裕のない中、学校側との様々な検討の結果、本番に近い環境でのリハーサルを実施。その結果、グループディスカッション中の生徒の皆さんの議論内容はリモートにいる講師には聞き取れない、しかし教壇に生徒が来て発表してもらえば講師は聞き取ることができることが判明。そしてこのリハーサル結果をもとに各講師は様々な工夫をこらしました。
各講師のサブテーマ : SDGを意識しつつ、以下のサブテーマを取り上げました :
SDG全体・SDGsを自分の問題としよう・自分の将来・活躍するために切り札・ジェンダー・食べること・多様性・エネルギー問題・異文化・貧困・不平等・医療
本番と振り返り
本番を迎えた2月1日。各クラスでは欠席者が数名出ましたがそれらの生徒も一部は自宅からオンラインで参加してくれたほど積極的な姿勢でした。

グループディスカッションする生徒のみなさん
授業直後の先生方と講師全員によるオンライン反省会では、講師一同から、生徒のみなさんの、グループディスカッション発表時の内容のすばらしさ、議論の活発さ、自立していること、など賞賛の声が相次ぎました。
生徒のみなさんおよび先生方の振り返りシートを拝見すると、オンラインでも、学校側が当初からご要望された「生徒たちができるだけ討議、意見交換、質疑応答をしてほしい。」について、限界は感じつつもかなりの程度までは達成できたのではないかと考えています。主な要因は、①コロナ禍でご多忙を極めながらも先生方の大変なご尽力と学校側の協力体制、②自立し自分の考えや意見をきちんと持っている生徒のみなさんのすばらしさと授業参加意欲、③ディレクトフォース講師陣の熱い思いと準備、そして④3コマ・合計150分の授業時間という比較的余裕のある授業枠などが挙げられます。
生徒・先生のコメント :
以下に生徒のみなさんからの振り返りシートの抜粋をご紹介致します。
-
生徒 A:
「本当の失敗は、失敗しても立ち上がらないこと」という言葉をいただきました。これからの生涯も、失敗することがたくさんあるだろうけど、失敗を活かしてそれを次にどのようにつなげられるかを考えながら行動することが大切だと学びました。
-
生徒 B:
答のない問題をぶつけられたときは状況を理解し、深く考えることである。人と話すときは、相手の発言をまず肯定し、リアクションする、そして自分の意見と照らし合わせて、より具体性のあるよいものにできるよう吟味しとりこむ、ということが重要であるということを学んだ。人の意見は自分の見方を広げるすばらしいものである。
-
生徒 C:
私は将来海外の人たちと関わる職業につきたいと思っています。実際に海外の方と働いる方のお話を聞いてより意志が強くなりました。異文化とうまく付き合うためには広い経験を持つこと、固定概念をなくすことが大切だとうことがわかりました。早いうちからチャレンジすれば転んでも何度でも起き上がれることができるので目の前にあるチャレンジをつかめる人になりたいです。
-
生徒 D:
SDGsはあまり身近なことからでは解決しづらいと思っていたが、授業を通じて、自分たちにできること、早寝早起きなどの、健康管理から通じることができることを学んだ。進路で学びたいことは決まっていてSDGsにはつながらないと思っていたが学んだ知識を活かして、社会に役立つことを考えていきたいと思った。
-
生徒 E:
みんなと同じ多数派は安心するかもしれませんが、今後必要なのは確かな自分を確立し、自分の軸を作ることが大切だと思います。そのためにはネットで分かったつもりにならず自分の五感でいろいろなことを体験する、世界がどうなっているかを知ることが大切だと思います。これらのことはこれからの生き方で実践していきたいです。
-
生徒 F:
僕は教員を目指しています。やはり、クラスの中で平等に接してあげることができるのだろうか。そんな事が不安になります。僕は差別を厳しく言っています。(特に男女差別)自分の言っていることが正しいのかよくわからなくなります。今日の授業を通じてそのヒントを得ることがきたような気がします。
以下に先生方からの振り返りシートの抜粋をご紹介致します。
-
内村優 先生コメント(今回の授業の学校側責任者) :
(クラス別ではなくテーマ別グルーピングであったため)普段と違うメンバーと話し合うことで刺激があった。具体例を講師の実経験から聞くことで実世界の出来事として認識できた。生徒が発表し、問題点を指摘してもらい、再度考えて発表できたのはとてもありがたかった。当初は内容が難しいかと思ったが、生徒の振り返りシートを見ると、興味を持ち、内容理解もできたようだ。自分の人生に還元していきたいと思えるようで、言葉だけにならないように期待したい。
-
稲木美聡 先生
今、世界で起こっていること、異文化体験など、具体例を多く紹介していただいたので、生徒もイメージをもって話しを聞くことができたと思います。グループディスカッションを通して今まで当たり前に使っていた言葉、考えについて理解を深めることができました。オンラインでしたが、発表に対してコメントいただいたり質問にも答えていただいたりしていたので、特に問題なく講義を受けることができました。
最後にディレクトフォース講師陣の感想をご紹介します。
-
見目久美子 会員 :
SDGsの基本および社会に出た時に必要なこと(講師の経験をふまえ)の2テーマについて、講義、グループディスカションと発表をおこないました。SDGs各項目について現状(数値)を生徒さんに説明を進めたところ、興味を持って参加し自分ごととしてとらえてくれたのが印象的でした。グループディスカッションではひとりひとりが意見を出し合い、発表もその後の意見交換も素晴らしく頼もしく感じました。オンラインのため講師のファシリテーションには限界があり、担当の先生の細やかなサポートに感謝いたします。
-
盤若浩孝 会員 :
オンラインとなり、画面越しに討議の様子を見守りながら、正直もどかしさを感じました。しかしグループ発表を通じ、「異文化に接することで、私たちは、様々な価値観に触れ、新しいルール、価値観を生み出すことにつなげる」とのメッセージをまとめてくれたのを見て、確かな手ごたえを掴むことが出来ました。彼・彼女たちの未来への期待が大きく膨らむ一方で、その分、リアルで直接話し合いたいとの思いがますます募りました。
-
内山正人 会員 :
オンラインでの授業になりましたが、先生の協力を得てエネルギーに関するシミュレーションゲームをやってみました。4チームに分かれて、生徒は楽しくも真剣に将来のエネルギーをどうするかを話し合い、トレードオフに悩みながら方針を決めて競い合っていました。このゲームと講義を通じて、エネルギーや環境について身近で自分たちや将来世代の問題だ、ということを体感し、加えて、エネルギーが十分に供給されないことが、貧困やジェンダーなど様々な社会課題に繋がっていることにも気づいてくれたことは、大きな成果だったと思いました。
以上
(授業支援の会 矢ケ崎隆二郎、根塚眞太郎)