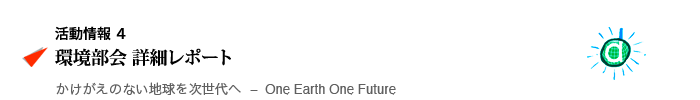
(12/05/13)
第7回DFエコ基礎講座
「グローバル経済と環境」
経済と環境の歴史展開と現代」
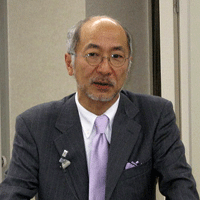 慶応義塾大学の経済学部長も務められた細田衛士経済学部教授(写真右)を講師にお招きして,「ディレクトフォース環境部会・環境学習分科会」の主催で第7回DFエコ基礎講座「グローバル経済と環境」 経済と環境の歴史展開と現代 が4月17日(2012年)に開催されました。当日は74名の方々が参加され盛況のうちに講座が行われました。
慶応義塾大学の経済学部長も務められた細田衛士経済学部教授(写真右)を講師にお招きして,「ディレクトフォース環境部会・環境学習分科会」の主催で第7回DFエコ基礎講座「グローバル経済と環境」 経済と環境の歴史展開と現代 が4月17日(2012年)に開催されました。当日は74名の方々が参加され盛況のうちに講座が行われました。
主な内容は次の通りです。
1.環境問題とは何か<経済発展と環境問題>
- 環境問題とは⇒自然環境が損なわれ,それによって人間の生活・健康も影響を受けるという問題。
- 自然環境と経済は相互関連している。経済活動によって環境破壊はもたらされる。ほとんどの環境問題の根源には人間の経済活動がある。特に近現代では。
- 経済活動と自然環境の保全を如何にして両立させるかが問われている。
- 欧米人は自然と対峙してきたが,日本人は自然の有り難さを知っている。
- 社会構造も,「共産主義」と「市場経済での格差社会」の中間の社会構築は難しい。環境問題も経済発展と環境保全,どちらかということではなくその中間はないかを探っている。未だ答えはないが。
- 環境問題を解決するためには,経済活動に一定の制度的制約を課す必要がある。
2.歴史の中の環境問題
- 縄文時代前期は別として,ほとんどの時代,人間生活は環境に大きな脅威を与えてきた。環境に負荷を与えていない人間などどこにもいない。
- 農業による環境圧力
- 半乾燥地での灌漑は,塩害をもたらし,栄養塩素が地表に噴出し,地味は劣化
- 牧畜による羊やヤギは植生を破壊し,土地は劣化
- 農業生産が増加すると人口も増加。人口が増加すると新たなる開墾が始まる。農業生産の拡大は森林の伐採につながった。11〜13世紀の大開墾時代にヨーロッパの森林は破壊された。
- 森林資源は枯渇し,エネルギー資源は石炭へと変わった。
- 人間を豊かにした技術は,環境を貧しくした。
- 技術だけでは環境問題を解決しない。むしろ問題を起こしてしまう。
3.近代の環境問題:鉱害と公害
- エネルギー革命と資本制生産の発展。
- 市民社会の形成:欲望の解放 。
- 鉱業による公害と工業による公害。
- 農業の環境破壊とは相の異なる環境問題が起こる。
- 経済成長と環境保全は両立しないのか
- 1970年政府は,公害対策基本法改正,水質汚濁防止法,大気汚染防止法などの法律を成立。
- マスキー法をアメリカは闇に葬ったが,日本は実施。環境負荷の小さい日本の小型車が国際競争力を持つようになる。
- 企業の公害防止努力が本格化。
- 一定の制度的な制約条件があったからこそ経済成長と環境保全が両立できた。
- 経済成長をしながら環境負荷は減った‥‥環境クズネッツ曲線の仮説
- 経済の成長の初期は環境負荷は高まる
- しかし,ある一定の所得(5,000〜8,000ドル)を超えると,環境負荷は小さくなるという仮説がある。
4.新しい環境問題:地球環境問題
- 気候変動問題,成層圏オゾン層減少問題,砂漠化問題,酸性雨問題,廃棄物の越境移動問題など 。
- 解決には,国際協調が必要⇒国益が絡んでくる。
- オゾン層破壊防止の協定は実行できたが,京都議定書は発効したもののアメリカが不参加。
- ソーラーパネルその他の分散型電源技術を上手く組み合わせれば新たな付加価値が生まれる可能性が大きい。
- 原発に依存せずとも安定的な電力供給をする可能性が高まっている。
- もう一つの重要な問題は,廃棄物問題。海外に,とりわけ発展途上国に廃棄物が漏れ出している。
5.グリーン・キャピタリズムの到来
 経営,市場運営,経済政策の根本理念を変える必要がある。グリーディー・キャピタリズムからグリーン・キャピタリズムへ。
経営,市場運営,経済政策の根本理念を変える必要がある。グリーディー・キャピタリズムからグリーン・キャピタリズムへ。- 一部の先進企業はものすごいスピードで環境対策を行っているが,まだまだ温度差がある。
- 今こそ経営者の環境への「哲学」が問われている。
- 環境保全とビジネスを両立させる理念と実現性の高いガバナンスが必要。
- グリーン・キャピタリズムに向けての「国家戦略」が必要。EUは,環境保全の国家戦略,理念がしっかりしている。
- 循環型社会では Japan Model が作れるが,多くの企業がそれに気づいていない。しかも,それがデファクトスタンダードになりえる。
- 日本の環境保全技術は高い。
- 重要なことは,要素技術だけでなく,要素技術を繋ぎ合わせる経済システムを作ること。
6.終わりに:ジャパンモデルの提示
- 日本の良いところ 心をこめること
《例》
- 飛行機の整備が終わって離陸する飛行機に頭を下げる
- 新幹線の清掃が終わって車両に頭を下げる
- 日本のエネルギー効率は大変良い。更にシステム改善をし,それを世界標準にすべき。
- 環境保全とビジネスが両立する21世紀型のグリーンキャピタリズムの理念と具体的施策を表明すべき。
- 要素技術とシステムを対として考え,日本の低環境負荷型経済のアイデアを東アジアに広げるべき。真の意味でアジアの繁栄,自然環境との調和を求めて。
以上
(文責:神山 利)
