2012/11/15(No137)
「アインシュタインのヴァイオリン」と教育問題
David Shapiro
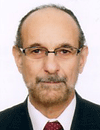 被災地をはじめとして各地の小中学生に「出前理科実験」を提供しているDF教育部会理科実験グループは、8月に東京フォーラムでも大々的なプログラムを行い、好評を得たそうだ。実験に目を輝かす子供たちが目に浮かぶ。
被災地をはじめとして各地の小中学生に「出前理科実験」を提供しているDF教育部会理科実験グループは、8月に東京フォーラムでも大々的なプログラムを行い、好評を得たそうだ。実験に目を輝かす子供たちが目に浮かぶ。
アルバート・アインシュタインも子供が好きだった。隣近所の子供たちと仲良く、一緒に水鉄砲合戦に加わったり、契約を結んでお菓子を報酬に学校の宿題を見てやったりしていた。天才呼ばわりされたアインシュタインだが、小さいころは、学校では目が輝かず問題児であった。彼が6歳の時、学校を訪ねた母親は先生にこう言われた。「あの子は頭が悪すぎて、残念だが勉強は無理だよ」と。
その母親とは、名前が通ったピアニストだったが、勉強がだめなら音楽をと自分のサークルにいるヴァイオリンのマエストロをあてがってアルバートにレッスンを始めさせた。しかし、うまくいかず何人ものマエストロが泣きながら家を出て行った。「面白くないから」とアルバートは練習もしなかった。そして13歳のとき、コンサート・ホールでモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを聴いた。「目から」ではなく、「耳からうろこ」というか、その音楽に惚れてどうしても自分も出来るようにすると決心したそうだ。これはアインシュタインの最初の大発見であった。以降、自ら励んでヴァイオリンをマスターし、やがてベネフィット・コンサートなどの舞台に立ちソリストとして演奏するようになった。
相対論も独学で発掘したが、自分はずっと音楽の中に身を置いて生きてきたという。音楽を通じて夢想し、物理研究が行き詰まるとすぐに音楽の世界に戻り、そこから宇宙を見つめ直すようにしたと自伝にも書いている。自分の体験を踏まえて、こうも言い残した。「最高の先生は、ただのしつけではなく、"愛"なのである」。
アインシュタインは教育問題にいろいろと言及した。教育の目的は子供の想像性、考える力、それに大自然、音楽、美しい創生に感激できる感受性を育てることであり、社会の本当の豊かさ、道徳、価値観はそこにかかっていると主張した。 世紀の科学者は、科学技術を恐れていた。自分の研究から生まれた原子力を含めて「今の人間にそんなものを与えるとは、3歳の子供の手にかみそりを持たせたようなものだ」と名言した。
かかる3歳児を心のある、責任感の強い社会人に育て上げるための教育とはどんなものであろうか。国際学力テストや偏差値も大事だろうが、従来の受身の姿勢を打ち破り一人ひとりの学生を主役に仕立て、頭が悪くて「ホープレス」の子供でも「アインシュタインのヴァイオリン」を自分の手に取るという教育環境づくりが最も肝心ではないだろうか。小学校から大学まで、教育の現場からその合奏が鳴り響いている日が来ないかと考える今日この頃である。■
ディヴィッド・シャピロ デイレクトフォース会員
元三菱商事米国法人社長補佐 三菱信託銀行米国法人社外取締役
三菱信託銀行国際本部顧問 日本国際大学 理事長特別補佐
現在流通経済大学教授 早稲田大学講師

