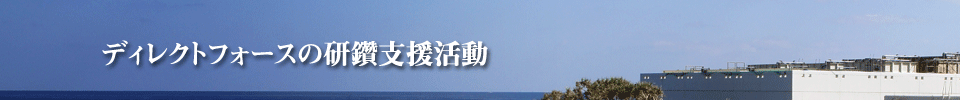2020年12月8日
 定期例会(総会・講演・交流会)
定期例会(総会・講演・交流会)
 DF勉強会(2020年)
DF勉強会(2020年)
2020年12月8日 更新
| 開催日 | タイトル | 講師 |
|---|---|---|
| 2020年 12月4日(金) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第8回「『三位一体』信仰に至るまで――異端と正統信仰」 |
秋山 哲 氏 |
| 2020年 11月4日(水) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第7回「キリスト教教理の深化――パウロとヨハネ」 |
秋山 哲 氏 |
| 2020年 10月8日(木) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第6回「聖霊降下と弟子たちの変容――ペンテコステとペトロ」 |
秋山 哲 氏 |
| 2020年 2月12日(水) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第5回「イエスの神宣言――父と私は一つ」 |
秋山 哲 氏 |
| 2020年 1月20日(月) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第4回「イエスは預言されたメシアか」 |
秋山 哲 氏 |
| 2019年 12月17日(火) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第3回「近代思想の先覚者――価値観を転換したイエス」 |
秋山 哲 氏 |
| 2019年 11月25日(月) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第2回「宣教したのは最大3年――その地上生涯」 |
秋山 哲 氏 |
| 2019年 10月11日(金) |
シリーズ「イエスとは誰か」 第1回 「イエスは実在したのか ーー 魔術使いか」 |
秋山 哲 氏 |
2020年12月89日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第8回「『三位一体』信仰に至るまで――異端と正統信仰」
 「イエスとは誰か」シリーズの最終回レクチャーがZoom方式で開催されました。概要は以下の通りです。
「イエスとは誰か」シリーズの最終回レクチャーがZoom方式で開催されました。概要は以下の通りです。
- 開催日時:12月4日(金)15:00から17:00まで
- 開催場所:651Studio(Zoomによるリモート・オンライン方式)
- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:24人
◇ ◇ ◇
これまでイエスの在世時代とイエスの直弟子である使徒の時代を話ししてきましたが、今回はイエスに直に接していない2世紀以降の「教父」と呼ばれる指導者たちの時代です。キリスト教教理が練り上げられていく過程ですが、信仰対象であるイエスとは誰かを巡る論争が激しく、正統信仰と異端が厳しく区分されて行きます。
異端信仰として排除されていった考え方の大きな部分はグノーシス主義と呼ばれます。グノーシスは、認識、知覚といった意味のギリシャ語で、プラトン哲学では重要な意味を持つ言葉です。パウロがその書簡の中で「不当にも知識と呼ばれている反対論」「空しいだまし事の哲学」と批判しているのはこの考え方だと思われます。
グノーシス主義と見られていて、2世紀から3世紀にかけて大きな勢力となったのはマルキオン派です。キリスト教最初の正典を造り上げ、この派の教会がたくさんありました。マルキオンは、旧約聖書が示す「義なる神」「厳しい神」とイエスの伝える「善なる神」「愛の神」を一つの神とすることを矛盾と捉え、「厳しい神」を創造神、「愛の神」を至高神とします。創造神は至高神の下位に位置づけます。このように複数の神を考えるのがグノーシス主義の特色です。善と悪が対立する二元論をもとにしているマニ教という宗教がありましたが、典型的はグノーシス思想です。
理性的に考える場合に受け入れやすいのですが、このような考え方は「アブラハムは主を信じた。主はそれを義(神の前に正しいこと)と認められた」という旧約聖書以来の信仰のあり方とは異なります。理性や洞察によってではなく、信じて神に従う、という信仰形態が旧約聖書、新約聖書を貫く考えです。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
また、神の愛、無私の愛(ギリシャ語でアガペー)が最も重要だと述べました。
もう一人のヨハネは、「イエスが愛した」といわれる最も若かった弟子です。彼は70歳以上になった晩年に、「ヨハネの手紙」「ヨハネの福音書」「ヨハネ黙示録」を著わします。
「ヨハネ福音書」はイエスの言行録ですが、他の三つの福音書とは内容がかなり違います。冒頭にある「言は神であった」という文章は哲学的に深いイエス理解として有名です。「言」はギリシャ語のロゴスの訳ですが、この言葉によってヨハネはイエスを示したのです。この文章はイエスを万物創造の神であると宣言しています。
また、イエスの言動、特に行った奇跡に関してその意味を深く掘り下げて説明しています。パウロと同様に「愛」の重要性を強調しました。
ヨハネが書いたとされる「黙示録」は理解が難しい書ですが、幻に導かれて終末を論じたものです。終末までには様々な困難や戦闘、裁きが続くのですが、「私はすぐに来る」というイエスが再臨し、最後には「神が人と共に住み、人は神の民となる」「万物が新しくなる」と預言されています。
イエスが「父と私は一つである」と宣言しているので、複数の神を導入するのは異端です。ヨハネ福音書の冒頭にあるように、万物は神であるイエスによって作られたという立場からは、創造神というものを別に建てるのも異端です。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
このような論争に決着をつけようとしたのは、キリスト教に入信し、キリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンチヌスです。AD325年に、ニカイヤ(ニケヤともいう)の町に200人以上のキリスト教指導者を集めて公会議を開き、「原ニカイヤ信条」を造り上げました。「父なる神」と「子なるキリスト」が「同じ実体」(ホモウーシオス)を持つ、つまり一つの神であることを確定したのです。
半世紀たったAD381年、テオドシウス帝がコンスタンティノープルで公会議を開き、信条を改めて議論しました。ニカイヤ信条で簡単に触れられただけであった聖霊の位置づけを明確にしようとしたのです。聖霊を、神、キリストと共に信じるべき神であることをうたった信条をまとめます。これを「ニカイヤ・コンスタンチノープル信条」といいます。「三位一体」のキリスト教神観が確立しました。イエスが復活して弟子に「父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい」と命じていますが、その言葉に裏付けられる信仰のあり方が確定したのです。
これが「イエスとは誰か」という問いに対するキリスト教からの答えです。現在キリスト教の教会で唱えられている使徒信条はこれを受け継ぎ、簡潔にしたものです。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
それでもなお教理論争が続きました。「神としてのイエス」と「人間としてのイエス」をどのように理解するか、です。
イエスの「神性」を重視する「単性論」と、「神性」「人性」の両立を主張する「両性論」が戦わされ、AD451年にカルケドンで開かれた公会議で決着がつきました。「両性論」が勝ったのです。イエスは「神性において完全であり人性において完全である」という理解が正統信仰となりました。「完全な神」であり、同時に「完全な人」である、ということです。この結果「単性論」の教会は離脱し、非カルケドン派と呼ばれるようになりました。
「三位一体」というキリスト教の神観はむずかしいのですが、コンスタンチノープルで教父たちが真剣に議論していたのと同じ時期に、中国では僧肇(そうじょう)という若い仏教僧が「本地垂迹」を説いています。「『本』(本質)と『跡』(現象)とは異なるが、不思議なことに『本』と『跡』は一つである」と。この考え方が日本に導入されて日本の神々はインド諸仏と同じだという明治以前の強固な信仰形態が生まれました。この考え方は「三位一体」論とつながるものがあります。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
また、新約聖書「ヘブライ人への手紙」は旧約聖書の信仰と新約の信仰の関係について「律法(旧約)には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません」と言っていることもかかわりがあります。影と実体は別々ではない、一つである、ということを言っているのです。時代的にはこちらが先ですが、僧肇の論と近似しています。この考えを進めると「実体」がイエスであり、「影」が父なる神となります。
2世紀にいたユティノスという教父がロゴス(言)と火の関係を述べていることも参考になります。火を分けて別のものに移しても元の火は減少せず、性質の変化は起こらいない、元の火も別の火も同じという論です。神とイエスの根源であるロゴスも火と同じだとします。ロゴスが神からイエスに、イエスから人に流れても、元の所にも、流れて行った先にも、同じロゴスが変化することなく存在する、と言っているのです。使徒信条がいう「同じ実体」論を理解する助けになります。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2020年11月9日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第7回「キリスト教教理の深化――パウロとヨハネ」
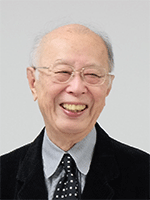 10月に再開された「イエスとは誰か」をテーマにした勉強会の第7回がZoom方式で行われました。概要は以下の通りです。
10月に再開された「イエスとは誰か」をテーマにした勉強会の第7回がZoom方式で行われました。概要は以下の通りです。
- 開催日時:11月4日(水)15:00から17:00まで
- 開催場所:651Studio(Zoomによるリモート・オンライン方式)
- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:29人
◇ ◇ ◇
前回レクチャーした「聖霊降下」は一般的には分かりずらいものです。体験者も、自分と神の間の秘事と考えてか、多くは語りません。明確な体験として記録されている一つ、数学者パスカルの死後に胴着に縫い付けられて発見された布切れを紹介します。「1654年11月23日、夜十時半ごろより零時半ごろまで」と記された布切れには「火」という文字に続いて「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者、識者の神ならず。イエス・キリストの神。汝の神はわが神とならん。世は汝を知らず。されどわれ汝を知れり。歓喜、歓喜、歓喜の涙」とパスカルの聖霊体験が書き記されていました。
今回はキリスト教教理の根幹を確立したパウロとヨハネについて述べます。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
パウロはイエスの直接の弟子ではありません。彼はユダヤ教についての教育を積んだ青年で、イエスの教えは間違っているという立場からイエスに従う人たちを迫害、弾圧していました。迫害のためにダマスコに向かうとき、ダマスコ門外で「なぜ私を迫害するのか」という天からの声を聞きます。「主よ、あなたはどなたですか」という彼の質問に「あなたが迫害するイエスだ」という答えがありました。パウロにとっては驚天動地の答えです。これが「パウロの回心」といわれる出来事です。
パウロは、荒野にこもって考えを整えて、キリスト教宣教に乗り出します。彼は旧約聖書に精通していました。ローマの市民権を持ち、ギリシャ語を話しました。この能力をもって現在のトルコ、ギリシャに3回の大宣教旅行を行います。捕らえられるとローマ皇帝に上訴し、移送されたローマからスペインにまで宣教を展開しました。
この間に各地の信徒にたくさんの手紙を書いています。それが新約聖書の半分を占めるパウロ書簡です。この中で、イエスが万物を創造した神であること、人間の罪を担って十字架にかかり、復活したというキリスト教教理を展開します。
特に重要なのは、ユダヤ教が強調する戒律厳守ではなく、神を信じることだけによって人間は救われるという「信仰義認」を明確にしたことです。何らかの行いが重要なのではない、ただ信じて神に従うこと、これが人間救済の筋道だというのです。後年この考えに気付いたマルチン・ルターは宗教改革に乗り出しました。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
また、神の愛、無私の愛(ギリシャ語でアガペー)が最も重要だと述べました。
もう一人のヨハネは、「イエスが愛した」といわれる最も若かった弟子です。彼は70歳以上になった晩年に、「ヨハネの手紙」「ヨハネの福音書」「ヨハネ黙示録」を著わします。
「ヨハネ福音書」はイエスの言行録ですが、他の三つの福音書とは内容がかなり違います。冒頭にある「言は神であった」という文章は哲学的に深いイエス理解として有名です。「言」はギリシャ語のロゴスの訳ですが、この言葉によってヨハネはイエスを示したのです。この文章はイエスを万物創造の神であると宣言しています。
また、イエスの言動、特に行った奇跡に関してその意味を深く掘り下げて説明しています。パウロと同様に「愛」の重要性を強調しました。
ヨハネが書いたとされる「黙示録」は理解が難しい書ですが、幻に導かれて終末を論じたものです。終末までには様々な困難や戦闘、裁きが続くのですが、「私はすぐに来る」というイエスが再臨し、最後には「神が人と共に住み、人は神の民となる」「万物が新しくなる」と預言されています。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2020年10月11日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第6回「聖霊降下と弟子たちの変容――ペンテコステとペトロ」
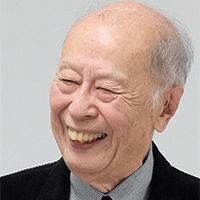 2月に行われた第5回以降中断していた「イエスとは誰か」レクチャーがZoom方式で再開されました。概要は以下の通りです。
2月に行われた第5回以降中断していた「イエスとは誰か」レクチャーがZoom方式で再開されました。概要は以下の通りです。
- 開催日時:10月8日(木)15:00から17:00まで
- 開催場所:651Studio(Zoomによるリモート・オンライン方式)
- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:24人
◇ ◇ ◇
前回話したように、イエスは「父と私は一つである」と神宣言をします。そのイエスのメッセージの中でまず実現した重要な出来事は「聖霊が降る」ということでした。イエスは最後の晩餐の席上で、自分が天に上れば「弁護者」を地上に派遣する、という予告をします。英語で Another Counselor と翻訳されている「弁護者」をイエスは「聖霊」であると述べ、聖霊を受けた者が「地の果てまで」イエスの教えを宣教すると説明しています。
イエスの十字架刑から50日目、エルサレムの一室で祈っていた弟子たち、信徒たちの上に「炎のような舌」が現れ、一同が聖霊に満たされます。これがイエスの約束した最初の聖霊降下です。騒ぎに驚いて集まってきた群衆にペトロが初めて説教を行います。これは神が約束された聖霊降下である、十字架刑で亡くなったイエスは復活し、天に上り、人類を救われるのだ、という長文の説教です。
これを聞いた群衆が続々と洗礼を受け、大きな集団となった、と使徒言行録は書いています。こうしてキリスト教がスタートするのです。
実は、イエスの弟子たちはユダヤ教の神学を学んでもいない「無学な人たち」でした。イエスと行動を共にしながら、正しいイエス理解をすることができませんでした。イエスに叱られてばかりでした。ペトロはかなり早い段階でイエスを「神の子」と表現するのですが、イエスが逮捕されるとイエスを「知らない」と否定します。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
そのペトロが聖霊降下を受けると立ち上がって見事な説教を行い、多数の信者を獲得するのです。
説教を行っただけではありません。奇蹟を行います。歩けなかった人に「立って歩きなさい」と命じるとその人は躍り上がって歩きます。女性の弟子が死んだのを生き返らせることもします。イエス在世中に弟子が奇蹟を行ったことはありません。聖霊を受けた結果、上からの力を受けて、イエスと同じように奇蹟も行えるようになったのです。
また、ペトロが見た夢によって、ユダヤ教の厳しい食事規定は採用されないことになり、選民であるユダヤ人とそれ以外の異邦人という区別もなくなります。異邦人にも聖霊が降るようになります。こうしてユダヤ教の中から生まれたイエスの宗教がキリスト教として別の歩みを始めることになります。
ペトロの信仰内容は新約聖書の「ペトロの手紙Ⅰ、Ⅱ」で理解できます。イエスが天地創造の以前から神と共に存在した、イエスは十字架上で死ぬことによって人々の罪を取り除き、人は神の前に正しく生きることになった、キリストの信徒は試練を通して神を崇めるべきである、神はすべての人が悔い改めるのを忍耐して待っておられる、といったことをこの手紙は述べています。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2020年2月27日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第5回「イエスの神宣言――父と私は一つ」
10月から始まった勉強会「イエスとは誰か」の第5回が開催されました。その概要は以下の通りでした。
- 開催日時:2月12日(水)15:00から17:00まで
- 開催場所:651会議室
- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:19人
◇ ◇ ◇
前回話したように、イエスは「父と私は一つ」と宣言しています。神と一体、神自身であるという立場はユダヤ教の歴史の中でどの預言者も取らなかった立場です。しかし、イエスはユダヤ教を無視して別の神を名乗ったのではありません。アブラハム以来のユダヤ教徒が信仰してきた神、つまり、ユダヤ民族と契約を結んだ神自身である、というのがイエスの立場です。彼の行動、言動は「聖なる四文字」であらわされる神の行動、言動ということになります。イエスも「父が私の内におり、その業を行っている」(ヨハネ福音書14:10)と明言しています。その立場に立つイエスがどのような宗教メッセージを発したのか。
一つの観点としてユダヤ教の改革ということがあります。すでに話しているように、イエスは、安息日のようなユダヤ教の戒律を必ずしも守らなかった。規定されているいけにえをイエスが神殿に奉納したという記録は新約聖書に出てきません。戒律にこだわる当時のユダヤ教指導層を手厳しく批判もしました。教条的に、表面的に戒律を守るのではなく、戒律の本来の意味を貫徹する、ということを要求しました。そのため、従来以上に戒律を拡大解釈する厳しい態度もとりました。
また、神のイメージを転換したことも重要です。ユダヤ教の神は「罪を罰せずにおくことは決してない」(出エジプト記34:7)と自己規定しているので、ユダヤでは「厳父」と認識されてきました。しかし、神は同時に「憐れみ深く慈しみに満ちた神」(出エジプト記34:6)とも宣言しています。イエスはこの「罪を赦す慈父」イメージを前面に押し出します。イエスは弟子たちへの告別説教で「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」(ヨハネ福音書15:13)と説きます。これがイエスの十字架刑の意味内容であり、愛の宗教と言われるキリスト教の基本となります。
しかし、イエスはユダヤ教の改革者では終わりませんでした。旧約聖書が予告している「新しい契約」をユダヤ教に持ち込みます。
彼が持ち込んだ主テーマは、「神の国」です。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
旧約聖書にその言葉がない「神の国」の到来を、宣教開始から一貫してイエスは語り続けます。「神の国」という「新しいぶどう酒」を入れる「新しい革袋」としてキリスト教が生まれることになるのです。イエスのいう「福音」とは「神の国」を伝えることです。
しかし、「神の国」の具体的な内容は必ずしも明らかになっていません。イエスは常にたとえ話を用いて「神の国」を論じたからです。それが現世に出現するのか、霊的世界か、いくつかの受け止め方があります。イエスが、ピラト総督に尋問されたときに、「私の国はこの世のものではない」(ヨハネ福音書18:36)と明言しているので、私は霊的世界の話だと考えています。
では、「神の国」はどのようにして到来するのか。イエスの説いたところによると、「神の国」の到来は、世界の終末・審判とイエスの再臨と同時に起こることになります。
「神の国」とともに、イエスの宣教のポイントは「永遠の命」です。これも旧約聖書では使われない言葉です。イエスは自らの十字架刑を予告する場面で「それは信じる者が皆、人の子(イエスのこと)によって永遠の命を得るためである」(ヨハネ3:14)といったように、信じる者に「永遠の命」を与えることが最終目的なのです。
「神の国」に入り、「永遠の命」を得る条件は何か。社会的地位や富裕であることとは関係がない。また、口先で「信じる」というようなことではなく、すべてを投げだしてイエスに従うことが必要だとイエスは述べています。
また、「霊的に生まれ変わる」ことが重要だとイエスは強調しました。それは聖霊の
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2020年1月28日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第4回「イエスは預言されたメシアか」
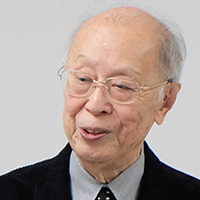 10月から始まった勉強会「イエスとは誰か」の第4回が開催されました。その概要は以下の通りでした。
10月から始まった勉強会「イエスとは誰か」の第4回が開催されました。その概要は以下の通りでした。
- 開催日時:1月20日(火)15:00から17:00まで
- 開催場所:651会議室
- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:21人
◇ ◇ ◇
これまでの3回はイエスを人として見る人性の面から説明してきましたが、これからは神としてのイエス、神性の観点から観察していきます。
イエスは誰かを考えるとき、「聖書は私について証しをするものだ」(ヨハネ福音書)というイエスの発言が重要です。旧約聖書は自分について前もって預言している、とイエスは言うのです。旧約聖書にはメシアについての預言がたくさんあります。これら預言を読んでみると、たしかに、イエスの生涯を前もって述べている、と考えることができます。
例えば、イエスの在世からみて何百年も前に編纂された「
これは、イエスの弟子ヨハネが哲学的に描いたヨハネ福音書のイエスと極めて似ています。ヨハネは「はじめに
また、旧約の詩編には「メシア詩編」と言われるものが9つあって、来たるべきメシアの姿が歌われていますが、イエスの地上生涯を、見てきたかのように表現しています。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
イエスより7百年も前の預言者、イザヤが書いたイザヤ書には「しもべの歌」といわれるものが4つあります。これらの中には、メシアが苦難を受け、「刺し貫かれる」と、イエスの十字架刑を想定することが書いてあります。
さらに、旧約のエレミヤ書などには、「新しい契約」という言葉が打ち出されています。神がモーセを通して人間と結んだ十戎を中心とする契約、つまり「旧約」を破棄して、神は人間との間で「新しい契約」を結ぶ、という意味です。これはイエスが宣べ伝えた「新約」を指し示しています。神が大きな政策転換をする、ということが予告されているのです。
常に敵対する周辺民族と争ってきたユダヤ民族はそのような苦難から逃れたいと願ってメシアによる統治と平和な世界を夢見ており、それがこれらのメシア預言に反映していると考えることができます。同時に、メシアの出現がいつになるのか、という期待感、焦燥感が強くなっていきます。詩編やイザヤ書などには、神に対して「いつまでですか」と問いかける言葉がたくさん出てきます。いつまで苦しまなければならいのか、という思いです。
そこにイエスが登場したのです。
先に話しているイエスとサマリアの女との対話の中で、女が「メシアが来られることは知っています」と言ったのに対してイエスが「あなたと話している私が、それである」と答えます。明快にイエスは自分がメシアだと宣言するのです。
「私がそれである」という表現は、旧約でも神の名乗りとして使われています。イエスはこの表現の延長線上で「私は道であり、真理であり、命である」「私が復活であり、命である」「私が命のパンである」「私は世の光である」といった言い方をします。神としての自己の本質をこういう形で表現するのです。これらは旧約で神が「私が全能の神である」と名乗ったのと同じ言い方です。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
イエスが神と自分が一体であると語った場面は新約にはいくつも見られます。イエスは神を父と表現するのですが、その父と自分の関係をこのように言います。「私を見た者は父を見たのだ」「私が父の内におり、父が私の内におられる」「私と父とは一つである」。
そこで分かるのは、旧約の預言しているメシアとイエスの姿に違いがあることです。旧約のメシアは、現世的メシアです。メシアによる統治によって平安な世界が生まれる、という考えです。また、旧約のメシアは、神から派遣される救世主です。
それに対して、イエスが主張するのは、神と一体、神と一つになったメシアです。しかも、このところは次回に詳しく話す予定ですが、現世的な平和社会を実現するとは言っていません。霊的世界をイエスは考えているのです。
イエスを一時は歓声を上げて迎えたユダヤ人たちが、イエスを十字架刑に処するのは、このようなボタンの掛け違えがあったからです。
少し別な観点を含んでイエスを説明している新約の「ヘブライ人への手紙」に触れておきます。この手紙は名前のとおり、ユダヤ人に対してイエスを説明しようとするもので、旧約と新約を一体として解釈するのが特色です。この書物の著者は分からないのですが、著者が言っていることは、旧約には実体がない、あるのは実体の影であって、新約に実体はある、ということです。その観点から、旧約の預言者たちが神からの言葉を伝達したのに対して、イエスは神の言葉そのものを語ったのだとします。
また旧約の大祭司が捧げるいけにえは、イエスが十字架によって自らをいけにえとして捧げ、人類の罪を贖ったことの影でしかない、とします。したがって、イエスはただ一回のいけにえであるのに対して大祭司のいけにえは毎年捧げる必要があった、というように書いています。ユダヤ教の考えるメシアとイエスの姿の違い、違いの意味を説明しているのです。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2019年12月24日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第3回「近代思想の先覚者 ―― 価値観を転換したイエス」
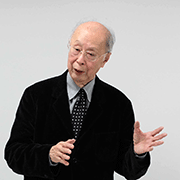 10月から始まった勉強会「イエスとは誰か」の第3回が開催されました。その概要は以下の通りでした。
10月から始まった勉強会「イエスとは誰か」の第3回が開催されました。その概要は以下の通りでした。
- 開催日時:Ⅰ2月17日(火)15:00から17:00まで
- 開催場所:760会議室
- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:15人
◇ ◇ ◇
今回の講義は、前回の第2回(イエスの地上生活)で積み残しになった「イエスの復活」から始まりました。復活は、イエスの地上生活と言えないかもしれないが、宗教の創始者が死んで復活する、というケースは他になく、キリスト教独特であり、これがなければキリスト教は存在しないとも言えます。復活したイエスは、弟子たちに「すべての民を弟子にし、洗礼を授けるように」と指示をします。
4つの福音書をもとにした前回レクチャーの補充の後、今回のテーマである「人としてのイエスの思想」へと進みました。イエスの言説は現在の人間にとって当たり前のことを言っていると受け止められる部分が多いのですが、これらの言説を2000年前に語り、行っていたという先進性は重要です。当時の価値観を転換させる思想をイエスが提示していたからこそ、キリスト教が世界の思想史、宗教世界に大きな影響を与えることになったのです。これがなければ、当時のユダヤで支配者ローマ帝国に抵抗して騒動を起こし、死刑になった何人もの巡回説教家の一人として、忘れられてしまったことでしょう。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
価値転換として分かりやすいのは、イエスが男女平等を実行したことです。当時、どの世界でも女性の地位は男性と比べて極めて低いものでした。無視されていたと言ってよい。ユダヤ教の戒律でも、ほとんど男性の思うままに離婚することができました。しかし、イエスは、結婚や離婚について完全な男女同権を教えています。性的マイノリティの受容もはっきりと述べているのは驚くべきことです。
イエスに付き従っていた集団には多くの女性がいて、それら女性の名が聖書にはたくさん記されています。十字架刑を見守るのも、イエスの復活を最初に知るのも女性たちです。福音書が記すイエスの活動の中では女性が重要な役割を果たしています。
女性差別だけではなく、様々な差別を無視してイエスは行動しました。ローマに奉仕する罪人と考えられていた徴税人の家に泊まるとか、一緒に食事をするとか、当時の社会では考えられなかった行動を取っています。戒律によって忌避することが厳しく規定されていたハンセン病患者に手を置いて癒し、共に食事したこともいくつも記録されています。現代の日本においてですらこのように行動する人が多いとはいえません。
歴史的経緯からユダヤ人が差別し、付き合うことも話をすることもなかったサマリア人の地方をイエスは旅行し、そこでサマリアの女性と1対1で対話を行います。ユダヤ教と異邦人の宗教が一つになる、という宗教上極めて重要な考えをイエスはこの異邦人の女性に伝えるのです。これは、女性差別と民族差別をともに完全否定する、無視する行動です。
「よきサマリア人」というよく知られた説話では、あえてユダヤ教の祭司とサマリア人を例示して、サマリア人の方が、隣人を愛する行動をとったと称賛しています。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
ローマ軍の隊長の娘を癒し、この隊長の信仰心を高く評価する話も、選民ユダヤと異邦人という区別、差別を乗り越えています。隣国フェニキアで異邦人の女性の子を癒したことも聖書は伝えています。
このように差別を排除する考えかたは、個の確立、自由意思の確認へと進みます。「放蕩息子の譬え」としてよく知られている説話がそうです。父親の生前に財産の分け前を要求して受け取り、その金を乱費して使い果たし、苦境に陥った男が父の所へ帰る。父は大歓迎して宴会を催す。父に従い続けている兄が怒るのを「失われた者が帰ってきたら歓迎するのが当たり前」と父はたしなめる。このストーリーを神の愛を示すたとえ話と受け取ることはもちろんよいのですが、放蕩息子の自由意思、自己決定を肯定する話と理解することができます。神を捨て、また神に帰る自由を人が持つ、という理解をするなら、信教の自由さえも表しているといえるでしょう。
イエスは宗教学者などが権威を振り回すのを嫌悪しました。ユダヤ教の重要な戒律となっている安息日をイエスは必ずしも守らず、安息日にも癒しの行為を実施しました。「安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではない」というイエスの言説は、宗教的権威を否定し、戒律をも自由に解釈することを許しています。
個人よりも集団を優先する古代社会にあって、イエスが目標としたのは、権威主義や、不平等、あるいは差別のない公正な社会でした。金持ちが地獄で苦しみにあい、貧乏だった人が天国に行く、といった話をしていることは、人としてのイエスが社会改革を見据えていたことを示していると思います。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2019年12月1日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第2回 「宣教したのは最大3年 ―― その地上生涯」
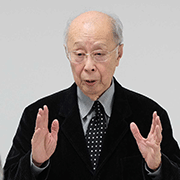 10月11日に始まった一神教シリーズの「イエスとは誰か」の第2回が開催されました。その内容を報告します。
10月11日に始まった一神教シリーズの「イエスとは誰か」の第2回が開催されました。その内容を報告します。
- 開催日時:11月25日(月)15:00から17:00まで
- 開催場所:760会議室
- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)
- 参加者:20人
◇ ◇ ◇
10月の第1回は、「イエスは実在したのか」をテーマにし、古代史に現れるイエスや、当時の社会情勢を説明、イエスの宣教開始当時の様子を述べた。
今回は、イエスの宣教開始から十字架上での死にいたる地上でのイエスの活動、つまり「公生涯」を概観した。
共観福音書と言われるマタイ、マルコ、ルカによる福音書でみると、イエスの活動はイスラエルの北部、ガリラヤ周辺で宣教し、最後にエルサレムにいって十字架にかかる、ということになり、公生涯は1年ほど、ということになる。
一方、ヨハネの福音書では、イエスはガリラヤとエルサレムを行き来し、エルサレムへは4回訪れている。この記述に従うと、イエスの公生涯は3年あまりということになる。
いずれにしても、イエスが地上で宗教的な活動を行ったのは極めて短期間である。ユダヤ教のモーセ、イスラムのムハンマド、あるいは釈迦、孔子などと比べて比較にならないほどの短い期間である。その間に、後刻説明するような宗教的に、社会的に、世界を転換させるまでの大きな影響を与え、いまにいたる世界最大級の宗教を築いたことを考えると、人間としてのイエスは並外れた人物である。
人間としてのイエスの性格をみると、一つは「愛の人」ということになる。しかし、ここで言う「愛」は、新約聖書を記述しているギリシャ語では「アガペー」であって、「無私の愛」「神的愛」「友のために命を捨てる愛」を意味する。日本語で愛、英語でLoveと訳されているものとは違っていることが重要である。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
イエスと、第一の弟子であるペトロの問答が聖書にあるが、二人の話は「愛」を巡ってすれ違う。イエスは「アガペー」で質問し、ペトロは、友人愛を意味するギリシャ語「フィリア」で答えるためにすれ違うのだが、日本語聖書は、二人の発言をいずれも「愛」と訳しているため、すれ違いの意味が分からない。英語でもLove一言で記述しているから意味不明の問答になっている。
またイエスは、謙遜であって高ぶらない「謙卑」の人といわれる。最後の晩餐で弟子たちの足を洗い、しもべ(僕)のように仕えることを教えた。
平和主義でもある。しかし、気性の激しいところもあった。エルサレムの神殿境内で、「ここは祈りの家である、商売の場ではない」といって、商売している人たちの店をひっくり返すという乱暴なこともしている。さらに、当時、宗教的に指導的立場にあった人たちを口を極めて非難することを繰り返している。
もう一つ注目するべきことは、イエスの聖書的学識の深さ、堂々たる説話と内容の面白さである。イエスの周辺に集まった群衆といわれるほどの人々は、前回話したたくさんの奇蹟に驚くだけではなしに、イエスの説法に引き込まれたのである。
イエスは最終的に、エルサレムに入り、弟子たちとともに最後の晩餐を行ったあと、捕らえられ、大祭司によって「神を冒涜した」という宗教上の罪を宣告される。しかし、「政治的反乱を企てた」という別の理由を付けて、死刑宣告の権限を持つローマ総督のもとに送り込まれる。
十字架刑によってイエスは死を迎えるが、十字架上で彼が「成し遂げられた」という最後の言葉を残したというヨハネ福音書の記述は、彼が、神の計画に従って行動し、神の計画通りに、人類救済のために死を迎えたということを意味している。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)
2019年11月1日 (掲載)
シリーズ「イエスとは誰か」
第1回 「イエスは実在したのか ーー 魔術使いか」
新しい勉強会「イエスとは誰か」が始まりました。
2016年秋から行われた「一神教のもつれた糸はほぐせるか」、また、それを受けて2017年秋にスタートした「神と人間はどのように関わってきたか」という一神教に関するレクチャーの第3回目シリーズです。その第1回の概要は以下の通りでした。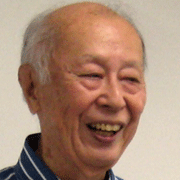
- 開催日時:10月11日(金)15:00から17:00まで
- 開催場所:760会議室
- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞常務、元日本イスラエル親善協会会長。DF会員)
- 参加者:20人
◇ ◇ ◇
当日の内容(概要)は以下の通りです。
最初にこの講義のねらいを説明しました。
イエスはキリスト教の信仰対象であり、「完全な神性」と「完全な人性」を併せ持つ唯一神という他に例のない設定になっています。このレクチャーは、分かちがたいとされる神性と人性をあえて区分して、それぞれの側面からイエスを説明しようとするものです。私は単なるキリスト教徒で、公式の神学教育を受けた者ではありませんが、あえてこのテーマに取り組みます。レクチャーは7回を予定し、各回のテーマは以下のとおりです。
- イエスは実在したのか ーー 魔術使いか
- 宣教したのは最大3年 ーー その地上生活
- 近代思想の先駆者 ーー 価値観を転換したイエス
- イエスは預言されていたメシアか
- イエスの神宣言 ーー 父と私は一つ
- ペトロやパウロはイエスをどう理解したか
- 激突する教父たち ーー 難産だった三位一体論
◇ ◇ ◇
第1回は、イエスが実在したかどうか、から話に入りました。キリスト教の経典である新約聖書にはイエスの伝記、言行録といえる4つの福音書があり、それ以外のパウロ書簡などにもイエスに関する情報がたくさん掲載されているが、新約聖書を除くとイエスに関する記録は極めて少ない。
ローマの歴史家タキトウスが書いたローマ帝国の歴史書『年代記』には、ネロ皇帝によるローマの大火に関連して「キリスト信者」が大量に殺害されたことが書かれている。またヨセフスの『ユダヤ戦記』には、イエスという賢人が奇蹟を行い、十字架刑に処せられたことが記載されている。ユダヤ教の口伝戒律をまとめたタルムードには「イェシュという人物が魔術を行い、民衆を錯乱させ、十字架にかけられた」という記事がある。
イエス実在の傍証はこのように多くはないが、イエスが実在しなかった、という仮説を立てると、新約聖書に記録されている高度な宗教思想、社会思想をだれが唱えたのか、なぜその人物が歴史の中に影を残していないのか、という面倒な疑問が生じる。
では、イエスが現れたころのユダヤ地方の状況はどうだったか。
アレクサンダーによる征服によってユダヤ地方にヘレニズム文化が持ち込まれ、その後を襲ったローマ帝国もユダヤ文化と相いれない偶像崇拝を持ち込んだ。この間、ユダヤ民族は圧迫されながら、神がいつの日か現れてユダヤを救われるに違いない、という強い希望を持つに至っていた。特に西暦紀元の少し前から、ローマに対するいくつもの反乱がおこり、この地方は騒乱状態といってもよい状況にあった。
⬈⬈⬈ ⬋⬋⬋
そのタイミングでイエスが生まれる。イエスは西暦紀元の4年ほど前に生まれ、西暦20年代の後半に十字架刑にかけられたと考えられる。
イエスの誕生物語はよく知られているが、4つの福音書はそれらの物語を同じように書いているか、といえばそうではなくて、ばらばらである。また、イエスの幼年期の情報はほとんどない。ヨセフというナザレ(ガリラヤ湖の近く)の大工ヨセフがイエスの父という役割で、イエスは大工仕事を手伝って成人したと見られている。
イエスが宗教人として活動を開始するまえに、洗礼者ヨハネという人物によって、ヨルダン川で洗礼を授けられる。その後、イエスも従う人たちに洗礼を行うが、ユダヤ教には洗礼というものがない。ここからユダヤ教とキリスト教の分化が始まる。
イエスは弟子を集め始めるが、弟子になる者には、家族、肉親との関係を立ち、財産を捨て、無条件でイエスに従うことを求める。弟子になった者たちも、イエスの一言によって、すべてを投げうってイエスに従うようになる。
イエスは、病を癒し、身体障碍を取り去るという医療行為によって名声を博し、広い地域から大勢の信徒を獲得していく。イエスの行った奇跡は、死人をよみがえらせることをはじめ、新約聖書に満載である。水をぶどう酒に変える、わずかなパンで5千人もの群衆を満腹させる、水上歩行など、さまざまな奇蹟を行った。タルムードが「魔術」と書くのも無理がないほどである。これら奇蹟をどう考えるかは、イエスの神性について説明するところで話す予定である。次回は、イエスの地上生活の後半を話しする。
◇ ◇ ◇
以上(秋山哲)
(編集註:本稿は秋山講師ご自身が記述されました)